- TOP
- >
- αM PROJECT
- >
- αMプロジェクト1994-1995 高島直之
- >
- αMプロジェクト1994-1995 vol.13 藤澤江里子
αMプロジェクト1994-1995 vol.13 藤澤江里子
1995年10月17日~11月11日
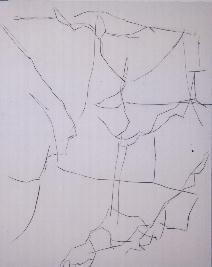
絵画の起伏と密度
高島直之
現代絵画のアポリアを辿っていくと、その集約された対立項のひとつに、象形か非象形かという問題に行きつく。ある既知の像(線描による輪郭として)が再現されること、あるいは、既知と思われる像が示唆されること、はたまた既知の像とは何か、を問うものがある。それでは、非既知の、非象形とは何か、と問われて即答できる人はいまい。とりあえず、すでにある、自然や、身の回りの物や風景の<形>を輪郭づけないこと、といえるし、それを排除したうえでの、絵画空間の創出である、ということができる。しかし、この象形性と非象形性の対立を<対立>と捉えて問題を設定すること自体が、正しいことなのか。画家にとって、制作中の画面に向かって意識的に既知の像を描き出すことがあっても、制作全体の時間において、すべて象形的であることに囚われているわけではないだろう。
いま当面しているのは、象形と非象形のふたつが、われわれの観念として、ここにある、という事実が重要なのである。そう見た時に、幾多の作家がさまざまな営みとして、このふたつの狭間で格闘していることの、さらに奥深い意味が明らかになるに違いない。個々の作家にとっての心理的実在性は多様であり、それは時に具体的でありながら、また時に抽象的であるはずである。そのめくるめく、イメージの往来において絵画は生まれる。
藤澤江里子が、注目されるのは、線描によって画面を統括しようとする、独特の意識とそのアプローチにある。作品を発表し始めた頃は、シェイプト・キャンヴァス(ベニヤ板に綿布張りなど)による、暖かい色味を用いる、面的な扱いによって、素朴な形象を定着していた。この時期に限定すると、必ずしも<線描>性は感じとれない。興味深いのは、90年頃から矩形の綿布や紙を使用するようになって、線への関わりが深くなってくる。
それでもまだ、面的処理は見受けられるが、線によって成立させる、恣意的な形象と括ることができるようになった。つまりは、矩形の、水平・垂直のフレームによって、線描性が加速されていった。とくに、パステルや木炭を使うようになって、黒を中心とするモノクラミックな線が、際立ってくる。そこにおいて、全面に黒く塗りつぶした(フロッタージュ手法を含む)ような仕事も出てくるが、もはやそれは、線が密に隣り合い、重なり、連なり合って<面>が立ち上がってくることが強調されている。
藤澤は、矩形という、絵画のもっとも基本的な前提、ゼロ地点に回帰することで、形象が孵化する次元に降り立った。パステルや木炭という、油彩画の下地の上に、最初にラフなあたりをつける材料を選んだのは、偶然ではない。いうまでもなく、このパステルや木炭は、油彩画のような奥深いイリュージョンを達成できるものとしてはない。藤澤は、その油絵の歴史が体現してきた「大絵画主義」と、自らの表現意識とのずれに気づいていたはずだ。
さて、ここに表わされた線による形象は何なのであろうか。基本的には、日常眼にする、あらゆる形象の断片から刺激を受け、その記憶を元にドゥローイングをし、そこから自分が気にかかっていた、欲望していた<形>を掘り出していく。したがって、筆勢によっておもむくまま自動的に出てくるわけではない。
本展において、綿布に木炭の4点は上記のやり方で一気に描き上げたものだが、キャンヴァス裏地にチョーク、紙にオイル・スティックの線的作品は、画像にとって、積極的とは思われない線の修正・打ち消しを行なっている。また、紙に黒のオイル・スティックで塗られた、面的な形象の仕事は、線でつぶしながら行きついた形態である。これらのヴァリエーションは、藤澤がこの間試行してきたことのすべてといっていい。ここに表わされた、線を基調とする、図像のありようを、既知のものと対比することは困難である。ただひとつ、既知のモデルを取り上げるとするなら、矩形のキャンヴァスに描かれた、制作行為を含めたところの<絵画>の存在であろう。
その絵画に現われた表面の下に、層となって備蓄された画家の視線のうごめき、これからマチエールが生まれ、幻影が起伏し、密度を高めていく、その充満した<始まり>の意識。それがそのまま藤澤の<主題>に吸い込まれて、そして開放されていく。そこには、魔術的な、内在化した、絵画の修辞学がある。
