- TOP
- >
- αM PROJECT
- >
- αMプロジェクト1994-1995 高島直之
- >
- αMプロジェクト1994-1995 vol.7 菊池敏直
αMプロジェクト1994-1995 vol.7 菊池敏直
1995年1月10日~2月4日
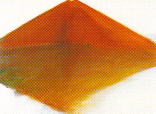
境界とプリズム
高島直之
菊池敏直は、1970年代の大半を美術大学の学生として過ごした。日本の現代美術の70年代は、ポスト・コンセプチュアル・アートの状況の下で、新たな主題を探しあぐね、さまざまな模索がなされていた。たとえば、当時やっと安価になりつつあったビデオシステムを利用したり、写真作品と立体とを組み合わせたり、また、鉄材と日常の生の物質とを関係づけるようなインスタレーションが試されていたのだった。
また同時に、立体派からミニマル・アートに至る、前衛的な絵画の革新過程で見落とされてきた、近代絵画の生成のシステムについての見直しが開始されていた。それは、物理的な支持体と表面において、いかにフィクティヴな平面(絵画の次元)が成立し得るのか、という問いかけでもあった。
そこで菊池を含む、より若い世代の画家たちは、その始原的なモティヴェーションを、点や線、色彩、さらに身体の動きなどに求めていった。つまりは絵画の主題を、観る側の視線に寄らずに、絵画を作り出すメカニズムにみていった。このことはひるがえって、外界のモノの形象をなぞらず、また心理的でアレゴリックな形態を抽き出すこともない、”何を描くか”という主題を喪失したあり方といえるだろう。具象か抽象か、という二元論から遠く離れていったわけである。
このアポリアは菊池の初期の仕事にみるように、点や線を顔料やオイルによってシステミックに分節化する手法に結びついていった。そのあまりに分析的な手つき。そこで突きあたったのは、絵画は表面にすぎない、という自明の原理である。そこから菊池はさらに踏み込んで、その対象化の口実としてセザンヌの「サント・ヴィクトワール山」を選び出した。その近景・中景・遠景を無視した、自然全体を物質として捉えるセザンヌの仕事の、構図や手のストローク、あるいは余白をモデルに、手によって解析的にいくつも転移させていった。
またモネの「水蓮」も同じように、その水面下の深奥性と水面の表面性をシュミレートし、水溶性の色鉛筆に水を含ませて滲みを表現し、水蓮の葉の円味を浮かび上がらせた。いずれも、セザンヌやモネの絵画を規範に、原画A→A’→A”・・・・・・というように、システムとして転写拡大してみせた。
ここで菊池の特異な発想が芽生えた。セザンヌもモネも、油彩によるオールオーヴァーの意識が画面に実現されている。ふつう、これらは部分でありつつ全体を成しており、逆もまた同様である。しかし、菊池は、その拡散しつつ収斂していく”曖昧な海”からひとつの記号を読みとった。セザンヌから<山>の形を、モネから<丸味を帯びた円>の形を取り出す。
それらは山そのもの、円そのものではないが、ひとつの画面から何らかのひとつの形を選びとった。このシステム的転移と、偶然ともいえる形の発見は、1986年にドイツ・シュトゥットガルト造形芸術大学に留学し、さらなる展開をみた。L・シャフラート教室で版画を学んだが、そこでリトグラフに出会い、偶発的な形象のオリジナル版に直接操作の手を入れることで、複製されながらいくつもの作品が”生産”されることに気づいた。
一方、あるドイツ絵画作品の、自然風景を層として分化させた、色彩の単一化した扱いに示唆を得て、紫とオレンジを混ぜた”茶”色に魅惑される。これは基本的に山や大地の色である。菊池は、ニュートン光学のスペクトルにはない”茶色”―しかもゲーテがいうような、白と黒の合い間にある色は”茶”であるという独特の自然観に感銘を受け、現在に至るまでこの色を多用していく。
いわばそれは、セザンヌやモネのニュートン的世界の境界を擦り抜ける、もうひとつの外界との接触の仕方とはいえまいか。菊池の仕事は、その意味でいま、屹立した表現たり得ている。同時に、70年代の膠着した美術状況をプリズムに通してできる、光跡のひとつにもみえる。
